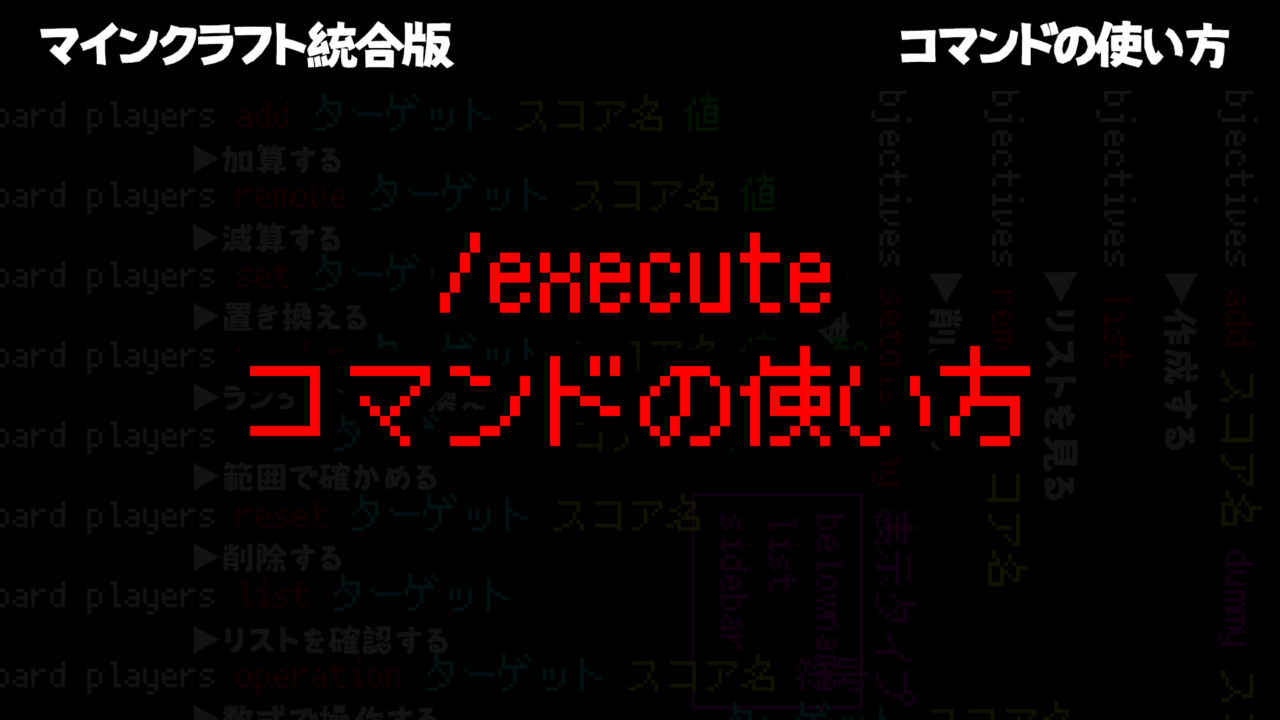マイクラ統合版はJava版とちがってデバッグ情報の表示機能が無いため、画面から得られる情報がそれほど多くありません。
普通にプレイしている分にはそれほど困りませんが、モブの湧きを調べたり、膨大に存在するエンティティの数を数えたりといった検証を行うにはコマンドで情報を補う必要があります。
で、そんなときに絶対的に便利なのが『execute』コマンド。
ここではこの万能コマンドの使い方を紹介します。
【重要】1.19.50からexecuteの構文が大きく変更されました。
この記事でも新構文を使用して解説していますが、構文の一覧は以下をご覧ください。
▶【マイクラ統合版】executeコマンド構文の変更点
『execute』で出来ること
“execute”は直訳すると“実行する”という意味。
大まかな使い方としては『あらかじめ指定した条件に従ってコマンドを実行する』という命令を作ることができます。
使用例)モブの湧いた位置をマーキングする
個人的に検証時に良く使うのがこの「湧き位置マーキング」。
モブが湧いた位置を正確にマーキングできるので、例えば敵モブの湧き範囲を調べたり、アイアンゴーレムの湧き範囲を調べたりといった用途で重宝します。
使用例は以下。
/execute as @e[type=zombie] at @s run setblock ~ ~-1 ~ glass
順に解説すると、“/execute”のあとの“as @e[type=zombie]”で「すべてのゾンビ」をコマンド実行者に指定、その後の“at @s”では実行場所を実行者(ゾンビ)に設定することで、その後の”~”がゾンビの座標を参照するようになります。
“setblock ~ ~-1 ~”では先に指定した任意の座標~ ~ ~ のY座標のみ「-1」を加えることでゾンビの下のブロックを指定し、ブロックを置き換えます。
置き換えるブロックは例として“glass”としていますが、好みのもので構いません。
なお、湧き位置を調べるためには「湧いた瞬間にマーキングしてすぐ処理する」という動きを繰り返したいのでコマンドブロックを使用して
コマンドブロック1(反復/無条件/常にアクティブ)
/execute as @e[type-zombie] at @s run setblock ~ ~-1 ~ glass
コマンドブロック2(チェーン /無条件/常にアクティブ )
/kill @e[type=zombie]
とすることで、『湧いた瞬間にブロックを置き換えてマーキングすると同時にkillコマンドで処理する』という動作を自動で繰り返し行うことができます。
使用例)モブの数を数える
目視では数えられないほどの大量のモブをコマンドで数えることもできます。
例えば、モンスタートラップで一定時間に湧いたモブを処理せずに溜め、正確に数を数えたい場合は以下のようになります。
/execute as @e[type=zombie] run give プレイヤー名 diamond
ここでは”as @e[type=zombie]”でゾンビ(数えたいモブ)をコマンド実行者に指定し、”give (プレイヤー名)diamond”でプレイヤーにダイヤモンドを与えています。
実行者であるゾンビの数だけ”give”を実行することになるため、ダイヤモンドをもらえた数がゾンビの数ということになります。
このように、executeは他のコマンドと複合して使用することでかなり便利に使うことができるため、是非使いこなせるようになっておきたい万能コマンドです。